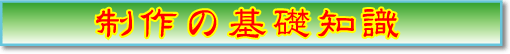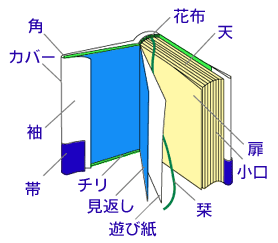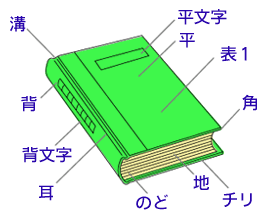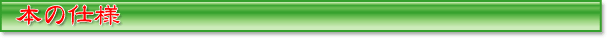
●判型/サイズ
本の大きさは20種類近くあり、内容や用途により使い分けされています。
下記は代表的な書籍の規格サイズです。
|
文庫判
|
105×148mm |
文庫本サイズ。
ポケットにも入る小型本。 |
|
新書判
|
103×182mm |
やや縦長のサイズ。
比較的小型本。 |
|
四六判
|
127×188mm |
単行本の大きさ。
手頃なサイズ、出版物で一番多い。 |
|
A5判
|
148×210mm |
月刊文芸誌等、長編の文芸物に多く使われている。 |
|
B5判
|
182×257mm |
週刊誌大の大きさ。
会報・研究誌やニュース性のある内容向き。 |
|
A4判
|
210×297mm |
美術書や写真集などに使われる比較的大きな判型。 |
|
※掲載以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。
|
●製本の種類
製本方式には大きく分類すると3種類あります。
| 上製本 |
ハードカバーと呼ばれ、表紙をボール紙に貼り中身を綴じ込む方式。
高級感と耐久性がある。金・銀の箔押し加工ができる。 |
| 並製本 |
ソフトカバーと呼ばれる。
厚紙の表紙に中身をくるむように綴じ込む方式。
書籍の中では一番多い。 |
| 中綴じ |
雑誌・リーフレット類に多く使用される。 |
|
※上製本につく箱もご用意できます。
|
●巻きカバー
表紙の上から巻き付けるものをいいます。カラー印刷されたものが多く、装丁家がデザインする場合がほとんどです。自費出版では使われる場合は少ないようです。
●表紙の種類
表紙の素材としては布と紙があります。布(布クロス)は上製本で使用され、表題は金や銀の箔をプレスして印字する『箔押し』となります。紙の場合は墨1色・2色・フルカラーなどの印刷となり、上製本・並製本いずれにも使われます。
●見返し
表紙の裏と本文との間に補強的に使われている紙。同人誌や定期刊行物などではつけないものが多いようです。
●扉
見返しの次にくるのが本扉です。書名や著者名をいれ、本文と別の紙を使うのが一般的です。俳画や毛筆を使用したもの、カラー印刷したものなどもあります。また、中扉・小扉・本文扉・章扉などとも呼ばれる本文中に挿入される扉もあり、ひとつの区切り的役割として使用されます。
これらの扉類は入れなくても差し支えありませんが、メリハリをつける意味であった方がよいかもしれません。
|
|
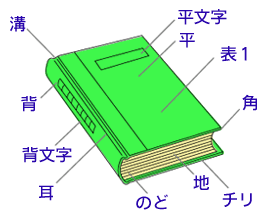 |
|
イラストの文字の所をクリックしてみてください。
詳しい説明が出てきます。
|
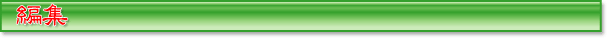
●原 稿
手書き原稿—なるべく読みやすい文字で原稿用紙に書いてください。
俳句・短歌等は、ノート類でも結構です。原稿は順番に並べ、目次や扉などは所定の場所に綴じ込んだ後、最初の原稿用紙から通し番号を書き入れていきます。
ワープロやパソコンで入力した原稿—フロッピーまたはCD等のデータと、プリントアウトされたものを合わせてお渡し下さい。その際、作成されたワープロの機種、ソフト名等もお書き添え下さい。 ●台 割
本を作る際の設計図とお考え下さい。通常の順番としては次のようになります。
1.表紙
2.扉
3.目次
4.まえがき
5.本文
6.合紙(中扉)
7.あとがき
8.奥付
一般的な並べ方ですので、追加・変更は自由にできます。
●校 正
手書き原稿から活字に起こす場合、当社で入力作業を行います。内部校正を入れて誤字・脱字の無いようにしておりますが、やはり間違いがある場合があります。また、ワープロやパソコンからの入力データであっても、文字化け等の変換ミスが起こる場合があります。これらを確認・修正する作業を「校正」と言います。
お客様が校正紙と原稿を照らし合わせ、間違っているところや変更をかける部分を赤字で校正紙に書き入れていきます。見過ごしてしまいますと、そのまま印刷されることになります。
また、文字の間違い以外にも体裁(文字の大きさや字数・行数等)や日付・電話番号等の確認等も再度行った方がよいでしょう。
●表 紙
表紙は本文と区分され、最初の表紙を「表(ひょう)1」、その裏を「表2」。裏表紙を「表4」、その裏を「表3」と呼びます。
●柱・ノンブル
ページの上部、または下部に見出しタイトル等の行がついている場合があります。これを「柱」と呼びます。また、ページの順番を表す数字を「ノンブル」と呼んでいます。
柱は入れなくても支障はありませんが、ノンブルは入れておいた方が読む側も読みやすくなるし、印刷工程でも重要な目印になるので省略するのは止めておいた方がよいでしょう。
●トリミング
使用する写真の一部分を載せたい場合、その部分を指示することを「トリミング」と呼びます。
使用する写真の上にトレーシングペーパー等の薄い紙をかぶせ、使用範囲を鉛筆で線を引きます。
●キャプション
キャプションとは、写真や挿絵などの下部に説明文や作者名を入れる文字のことを言います。
●奥付
本文の一番最後に入れる、いわば表札のようなページをいいます。通常は、書名・発行日・定価・著者名・発行所名・印刷所名などを入れます。
●文字の書体
文字の形には大別して「ゴシック」と「明朝(みんちょう)」があります。これをベースとして様々な書体が作られていきました。
文字には名前が付いていて、行書体・楷書体・教科書体等、様々な呼び方があります。また太さも細明朝・中明朝・太明朝・特太明朝等に区別されます。
●文字の大きさ
文字の大きさの単位には次の3つがあります。
|
号 数
|
昔の活版活字の規格 |
|
級 数
|
印刷業界の組版機(写真植字機)の規格 |
|
ポイント
|
国際的な文字サイズの単位。
パソコンなどの普及で一般に定着しています。 |
●紙の種類(厚さ・色)
紙には銘柄や色・厚さなどで実に多くの種類があり、表紙や本文などの用途で使い分けます。紙の厚さは重量の単位「キロ」で呼ばれています。
●布クロス
上製本の表紙に使用される布製のものです。印刷はできないので金や銀で箔押し(金型でプレスすること)をして印字します。
|